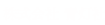副題:〈やまと言葉〉から考える
 著者:山本伸裕
著者:山本伸裕
ISBN:978-4-86228-083-1 C0010
定価 1,500円+税 324ページ
ジャンル[エッセイ・日本語]
発売日:2016年 5月13日発売
内容
〈やまと言葉〉にみる、日本人の「しなやかな生」への理想。
日本の風土・文化・生活から編み出されてきた〈やまと言葉〉は、歴史の試練を耐えぬき、日本人古来の知恵と心のあり方を現代に伝える宝庫。
聞き慣れた日本語も、その〈やまと言葉〉としての個々の源をたどれば、奥深く、時には意外な成り立ちが見えてくる──。
これらに共通するのは、「しなやかさ」「たおやかさ」と「調和」への理想であった。
・「優」とは「すぐれていること」だが、後にとりわけ「やさしさ」を表すものになった。
・「しあわせ」とは、複数のものごとを調和した状態に「仕合わせる」ことからきている。
・「あきらめ」は本来「明らめ」であり、つまり世界と自己への理解と了解からくる「さとり」の境地を意味した。
自己・宗教・喪失と罪悪・仕事などとの関わり方と照らし合わせながら、〈やまと言葉〉に内包された、日本人が育んできたものの見方と心のあり方をたどる。
目次
序論 〈やまと言葉〉で考える
第一章 日本人の「自己」の構造
第二章 日本人は「宗教心」に篤いのか
第三章 ニヒリズムを超えて
第四章 「仕事」と日本人
第五章 憂き世を浮き世に
著者について
著者 山本 伸裕(やまもと・のぶひろ)
1969年生まれ。東洋大学文学研究科仏教学専攻博士後期課程単位取得退学。
東京大学文学部思想文化学科倫理学専修課程卒業。文学博士(大谷大学)。
真宗大谷派・親鸞仏教センター研究員、東京大学東洋文化研究所特任研究員を経て、現在、東京医療保健大学講師。専門は倫理学、仏教学、日本思想史。
著書 『「精神主義」は誰の思想か』(法藏館)、『清沢満之集』(安冨信哉編、山本伸裕校注、岩波文庫)、『他力の思想─仏陀から植木等まで』(青灯社)、『清沢満之と日本近現代思想─自力の呪縛から他力思想へ』(明石書店)など。
序論より
・言葉は存在の住処
子どもの頃、友だちにあだ名を付けたり付けられたりしたという経験をもつ人も少なくないでしょう。あだ名を付けるというのは、それまで呼び名が存在しなかったところに、新たに名を生み出すという、ある意味、すぐれて創造的な行為とも言えます。誰かがふざけ半分に口にした言葉が、あだ名として定着するには、多くの人が命名の由来に共感・賛同し、周囲の人びとが一斉に使い出すということが必須の条件です。
また、あだ名など付けた経験をもたないという人でも、親にでもなれば、わが子に名前をつけるということをしなければなりません。もっとも、赤ん坊に名前を付ける場合には、役所に届け出をしなければならないわけですから、あだ名とは違ってその子は、生涯、否応なしにその名前で呼ばれることになるのですが、名付けという行為は、何もなかったところに言葉を創出するという点や、名づけられる対象が命名する人間の目にどう映っているかに深く関わっているという点で、本質的にはあだ名を付けるのとは変わらない思想的営みと言ってよいのです。
ところで、私はいま、この文章を、傍らに「マウス」を置いた状態で作成しています。「マウス」と言うのは、もちろんパソコンに情報を打ち込むための、あの入力機器のことです。掌サイズのこの機器が、なぜ「マウス」と呼ばれるようになったのか、その理由については、いちいち説明するまでもないでしょう。
“mouse”は、日本語に訳せば「ねずみ」です。ただ、日本人は、パソコンの外部入力装置のことを指す場合には、“mouse”という英単語を日本語に翻訳することなく使用してきました。そのことが、それを使う人の心理に及ぼす影響は、無視できないように思われます。この小さくて丸っこい物体が「マウス」と命名されたことで、多くの人が、多かれ少なかれ愛着を感じてきたことは確かでしょう。逆に、もし「ねずみ」などと翻訳されていたとすれば、はたしてどれほどの人がそれに愛着を感じたかは、甚だ疑問です。
ともあれ、“mouse”が、翻訳されずに「マウス」という言い方がされてきたという事実は、この語が日本語としてすっかり定着しているということを意味しています。パソコンが広く一般家庭に普及する以前の日本人で、「マウスを右クリック」と言われて、意味が理解できた人は、まずいなかったはずです。それが、わずか四半世紀のうちに、「マウス」と聞いて「ねずみ」と混同するような人は、ほとんどいなくなったのです。
英語では、ハツカネズミのような小型の“mouse”と、クマネズミやドブネズミのような大型の“rat”との間には、明確な認識上の区別が存在します。前者は、親しみを覚える小動物として、後者は、人間にとって気味の悪い、忌々しい生物として捉えられてきました。一方、日本語にはそうした概念上の区別は存在しません。日本人にとって、昔からネズミは比較的身近な存在で、蔵の穀物を食い荒らしたり、病原菌をまき散らしたりする厄介な動物として駆除の対象とされてきたのと同時に、昔話の中に登場したり、干支に取り入れられていたりもするように、ともに生活世界を形づくる伴侶動物的な存在でもあったのですが、「ねずみ」という一つの単語で言い表されてきたために、基本的に区別されることはなかったと言えるでしょう。
近頃は、「ねずみ色」という言葉をあまり耳にしなくなりました。「グレー」に取って代わられたからなのでしょうが、私が子どもの頃は、「ねずみ色」という言い方が一般的だったと記憶しています。このことが示しているのは、日本人は「ねずみ」という言葉に、元来、悪い印象を抱いていたわけではないということです。「ねずみ色」という言葉が廃れた背景には、普段の暮らしの中で野生のネズミを見かける機会がめっきり減ったこともあるのでしょう。しかし、それ以上に大きな要因として指摘し得るのは、日本人の生活とネズミとの関係、さらにはネズミという他者を含む生活世界全体に対する認識の変化ではないでしょうか。
ドイツの哲学者、M・ハイデガー(一八八九-一九七六)は、言葉は存在の住処だということを述べています。ハイデガーによれば、言葉というのは、単なるコミュニケーションのための手段でもなければ、人間が主体的に用いるものでもなく、逆に言葉が人間存在そのものを語るとされるのです。換言すれば、人間は言葉の使用をとおしてはじめて自己が置かれている世界に真向かいになれるということでもあるのですが、言葉というのは、要はそれほどまでに私たちのものの見方、世界観の形成に深く関与しているということです。
・現代日本語における多重言語構造
では、日本人にとってネズミは、元来、どのような存在として認識されてきたのでしょうか。私は、そのあたりのことを知る、もっとも簡単で効果的な方法の一つは、言葉の語源を訪ねることにあると考えています。
“mouse”にも、この英単語が誕生するに至った独自の思想的・文化的な経緯があることは間違いありませんが、「マウス」なる語は、日本人にとっては、どこまでも外来語として移入されたものにほかなりません。そのため、英米人とは異なる思想文化を背景に暮らしてきた人間に、“mouse”なる語を生み出した思想的な背景を、どの程度まで深く理解できるかと言えば、どうしても限界があると言わざるを得ないでしょう。そうした障害が存在している以上、日本語を母国語として生活してきた人間としては、言葉の背後に茫漠と広がる意味の世界について思いをめぐらす以前に、「マウス」なる言葉を、ひとまずそういうものとして記号的に受け容れるほかないのです。
一方、「ねずみ」というのは、日本人の暮らしの中から紡ぎ出された言葉です。したがって、この語の背後に広がる意味の世界、人間の暮らしとの関わりのありようを問うことは、「マウス」に比べてはるかに容易でしょうし、他者と世界を共有して生きている自己なる存在を、「ねずみ」という他者をとおして見つめ直すうえでも、裨益するところが大きいと想像されるわけです。
ただ、一概に「日本語」と言っても、「マウス」という言葉が日本語としてすっかり定着しているように、さまざまな文化に起源をもつ複数の言語で構成されているというのが、現在の「日本語」の実態でもある。もっとも、言葉が、単なるコミュニケーションの手段くらいにしか捉えられていないうちは、起源などというのは、特に意識されることもないのかも知れません。けれども、実際、私たちが現在、「日本語」として認識している言語は、大まかに、次に挙げる四つの異なる言語から構成されていると考えて差し支えないでしょう。
一、やまと言葉(和語)
二、漢語(中国語)
三、新漢語(翻訳漢語)
四、カタカナ語(音写語)
これら起源を異にする四言語のうち、最も古くから日本語として使用されてきたのは、言うまでもなく〈やまと言葉〉です。ここで「最も古くから」と言うのは、「人びとの身体性に根ざした」、「生活の内側から紡ぎ出された」という意味でもあるのですが、少なくともはっきりと断言できるのは、〈やまと言葉〉を生み出したのは、日本列島に暮らしてきた私たちの直接の祖先であり、この国独自の気候風土であるということです。
〈やまと言葉〉が、いついかなる経緯で生まれたのかについては、知る由もありません。また、ひとつひとつの言葉の由来にしても、多くの場合は、推測する以外にはないのが実状なのですが、日本人の発想の基底にあって、思想の原型を形づくっている言語が〈やまと言葉〉であるということだけは、疑う余地がないのです。
〈やまと言葉〉の次に、日本人にとって付き合いの長い言語が〈漢語〉です。〈漢語〉との付き合いがはじまったのは、中国大陸との交流が確認される、紀元前にまでさかのぼると考えられますが、日本語の語彙の中に本格的に〈漢語〉が取り入れられるようになるのは、仏教が伝来して以降のことであったと推測されます。
中国大陸を経由して日本にもたらされた仏教の経典は、すべて漢字で記されていたために、仏教の知識を吸収するには、〈漢語〉の習得が不可欠でした。日本に仏教がもたらされたのがいつなのかも、はっきりしたことはわかりませんが、六世紀半ばに朝鮮半島の百済から、仏像、仏具、経典一式が贈られたのが、仏教公伝の最初だったというのが定説です。
仏教の経典に記された〈漢語〉は、それまで〈やまと言葉〉だけを用いて暮らしていた古代人にとっては、当初は完全に異国の言葉だったわけですが、経典に書かれている思想内容を理解しようと、官僚僧たちが〈漢語〉の習得に努めたり、大陸の進んだ政治制度に学ぼうと、貴族たちが〈漢語〉の読み書きに精出した結果、もともと外国語であったことが意識されないまでに血肉化され、日本語の語彙の中に取り込まれていったと考えられるのです。
さらに〈漢語〉の後に日本語の語彙の中に取り込まれたのが、〈新漢語〉です。長いこと、キリスト教文化の影響が強い西欧諸国と実質的に断交状態にあったこの国が、一九世紀の後半に開国へと舵を切って以降、西欧の思想文化に起源をもつ諸概念が、一気に流入してくるようになります。そうした新たな時代状況に否応なく直面させられた近代の知識人たちは、西欧出自の新奇な概念を、一語一語、漢語風に翻訳するといった骨の折れる作業に取り組みました。〈新漢語〉は、そうした労苦の中から生み出されたのですが、これらは一見〈漢語〉のように見えて、中国文化に由来するものではないという点で、近代以前に輸入された〈漢語〉とは別種の言語として理解される必要があります。
明治期に活躍した日本の知識人たちが、中国人の力を借りることなく漢語風の翻訳語を量産できた背景に、漢文との長い付き合いの中で培われた〈漢語〉に対する素養の高さが指摘できることは言うまでもありません。ただ、私たち現代人には、中国由来の〈漢語〉と、日本生まれの〈新漢語〉とを見分けることは、それほど容易いことでありません。しかしながら、たとえば、「電話」とか「選挙」とか「自動車」などといった言葉が、近代以前の日本語に存在しなかったということくらいは、容易に推測がつくでしょう。
多重言語構造を有する現代の日本語の中でも、最も歴史が浅いのは〈カタカナ語〉です。〈カタカナ語〉というのは、外国語の発音を音写したものに過ぎません。その点で、限りなく「記号」に近いと言えるのですが、近代以前の日本語の中にも、〈カタカナ語〉に相当するものがなかったわけではないのです。
日本に伝えられた仏典の大半は、古いインドの言葉である〈梵語〉が中国で〈漢語〉に翻訳されたものです。実際、仏典の中には、「仏陀buddha」、「阿弥陀amit?bha」、「檀那/旦那d?na」、「娑婆sah?」等々、現代の〈カタカナ語〉に相当する音写語が数多く含まれています。また、周知の通り一六世紀以降、九州を中心に南蛮の文物がもたらされましたが、「煙草」や「合羽」、「金平糖」などは、ポルトガル語をそのまま音写した言葉です。
日本語を構成するこれらルーツの異なる四言語の混合比率がどうなっているのか、正確なところはわかりませんが、さほど大きな差はないように感じられます。ただ、これはあくまでもそうした傾向が見られるのではないかといった指摘に過ぎないのですが、〈やまと言葉〉は、主として日常生活において、〈漢語〉および〈新漢語〉は、主として学問や政治の場面で、〈カタカナ語〉は、ビジネスの世界でといった具合に、場面に応じて使用頻度に差があるということは言えるのではないでしょうか。(図1)
日本語を構成する四言語のうち、現在、急速に勢力を拡大しつつあるのが〈カタカナ語〉です。「ねずみ色」とか「灰色」とかの、古くからある〈やまと言葉〉が「グレー」に、「政権公約」などの〈新漢語〉が「マニフェスト」や「アジェンダ」などの〈カタカナ語〉に取って代わられるなど、近頃の〈カタカナ語〉の急激な増加には、目を瞠るものがあります。
私は、なにも新しい言葉を取り入れることが良くないと言っているわけではありません。ですが、近年、日本語の中に新奇な言葉が矢継ぎ早に取り込まれてきたせいで、それまでの地に足のついた生活のありようが見失われ、多くの人が、言い知れない、所在のない不安感に苛まれる要因となっているのだとすれば、新奇な言葉で溢れ返る言語状況がもたらす弊害について、いまいちど腰を据えて議論してみるべきではないかとも、思わずにはいられないのです。